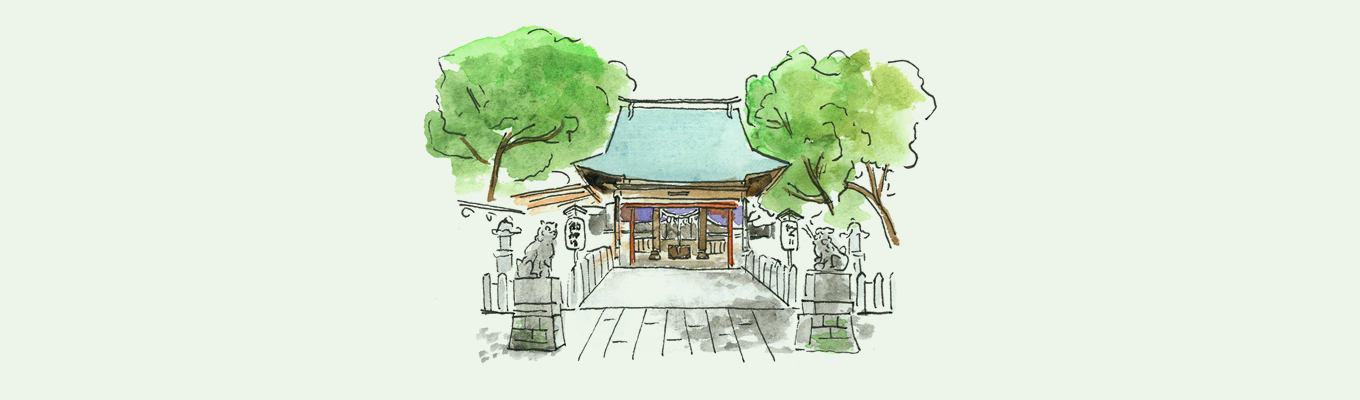
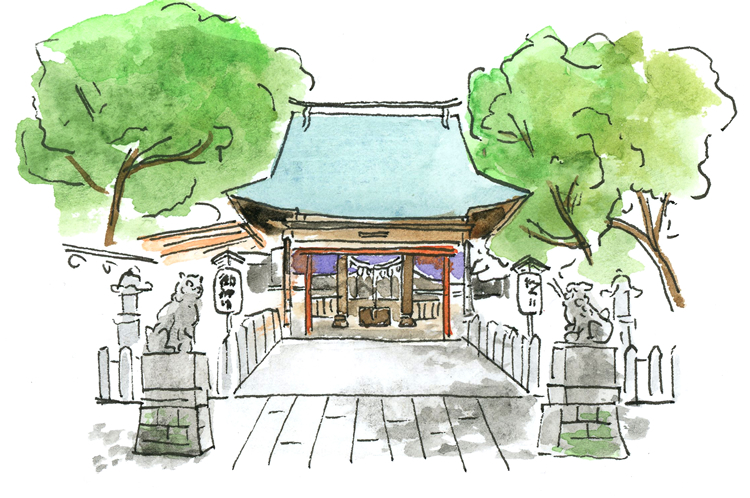
- HOME
- よくあるご質問
神社に寄せられる、よくあるご質問をまとめました。神社全般に対する一般的な質問を中心にしていますが、回答は星川杉山神社としてのものであり、地域や神社によっては考え方の異なるものもあります。特定の神社、地域に関する詳しい内容をお知りになりたい場合には、該当する神社へ直接お問い合わせください。
- ご祈祷
- お参り
- お神札・お守り
- 神棚
- 氏神様
- 結婚式
- 建築
- 神葬祭


ご祈祷料の支払い方法はどのようにすればよいですか?


のし袋に入れてお納めになるのが正式な形となります。



ご祈祷を受ける時にはどのような服装で行けばよいですか?


お宮参りや七五三詣などの改まった人生儀礼の場合には、男性はジャケットなど着用、女性もそれに準ずる服装が望ましいでしょう。厄除けや交通安全などでご祈祷をお受けになる場合は平服でも結構です。ただし神さまの前へ進むにふさわしい、きちんとした服装を心がけた方がよろしいかと思います。


ご祈祷を受けるのは代理人でも大丈夫ですか?


可能です。「代理参拝」として、ご本人の代わりにご祈祷をお受けいただけます。


予約は必要ですか?


皆様の願いに寄り添い、謹んでご祈祷を奉仕いたします。
混雑を避け、静謐な環境でお参りいただくため、事前のご予約をお願いいたします。
予約フォーム、お電話にて受付いたします。(受付時間9:00~17:00)


駐車場はありますか?


20台程度の駐車場がございます。


仏滅の日にご祈祷を受けても大丈夫ですか?


問題ありません。ただし、ご本人が気になるようでしたら避けたほうがよろしいかと思います。気持ちよくお参りいただける日を選ばれることをお勧めします。


カメラマンに同行してもらって良いですか?


可能ですが、以下注意事項をお守りください。
①祈祷当日、カメラマンには祈祷申し込み者とご一緒に受付にお越しいただきます。
撮影申請書にサインの上、名刺をお預かりいたします。
②撮影は、周囲の方に配慮しながら行ってください。撮影時間は約1時間を上限とします。
③カメラマンの社殿内への立ち入りはできません。
④カメラマンは参拝者駐車場を利用できません。公共の交通機関や近隣の時間貸し駐車場をご利用ください。
上記に反する場合、また職員が判断した場合には即退去いただくことがあります。


喪中なのですが、ご祈祷を受けてもよいですか?


ご家族などお身内の方が亡くなられた場合には、50日以降にお参りください。


着物の着付けはしてもらえますか?


着付けは行っておりません。ただし、お宮参りの際の「祝着」についてはお手伝いします。お声がけください。


授乳やオムツ替えの場所はありますか?


専用の部屋はございませんが、控室内にベビーケアスペースを設けております。


祝着のレンタルはしていますか?


しておりません。


団体祈祷の場合、社殿に何名まで入れますか?


約60名程度の広さがあります。


足が悪いのですが社殿では正座しなければいけませんか?


椅子をご用意しております。お声がけください。


七五三の時にカメラマンの手配はできますか?


スナップを得意とするカメラマンのご紹介をしております。当神社の撮影プランがございます。日程等は直接お問い合わせください。
Silver Salt Studio


安産祈願の腹帯はもらえますか?


腹帯のご用意はございませんが、お着けになる腹帯をお持ちいただければお祓いを行います。


厄除けのご祈祷はいつ受けるのがよいですか?


新年または立春が一般的ですが、厳格に考える必要はありません。心のおもむくままにおいでください。


いくつかの厄年表を見たのですが、神社やお寺によって年齢の違うものがあります。


伝統的な厄年の考え方は「男性25歳、42歳、60歳」「女性13歳、19歳、33歳、37歳」ですが、性別に関係なく、九星などの星回りに基づいて災いに遭いやすいとされる年にも「方位除け」「八方除け」を行う場合があります。地域性もあり、統一されたものではありませんので、神社やお寺によっては該当する年が異なることもあります。


厄年ではないのですが、厄除けをしてもらうことはできますか?


可能です。ご相談ください。


車椅子でも大丈夫ですか?


当神社社殿は木造の伝統的な様式で靴を脱いでご昇殿いただく構造上、制限がございます。
1. 手動車いすをご利用の方(昇殿可能)
段差が多いため、安全確保のため、必ず介助者様のお付添いをお願いいたします。神職・巫女もできる限りお手伝いさせていただきます。
また室内の為、タイヤのふき取りやタイヤカバーのご持参にご協力ください。
2. 電動車いすをご利用の方(昇殿不可/外でのご奉仕)
電動車いすでのご昇殿は、床の構造保護のためお断りせざるを得なくなりました。
【社殿の外でのご祈祷】
電動車いすの方や、昇殿が困難な場合は、社殿の外の参拝しやすい場所にて、心を込めてご祈祷を奉仕させていただきます。
ご神前と変わらぬ真摯な気持ちで、厳粛に祭事を執り行いますのでご安心ください。
3. ご来社前にご連絡をお願いいたします
車いすでのご来社、特に外でのご祈祷をご希望の場合は、ご予約の際に必ずその旨をお知らせください。


近くに会食のできるところはありますか?


七五三の前撮りは出来ますか?


ご祈祷を受けられる方のみご相談を受け付けております。
「撮影のみ」の方は受け付けておりません。


何時から開いていますか?


お参りはいつでも可能です。ご祈祷のお申し込み、授与所については9時から16時30分までとなります。お正月や例祭など特別な期間については随時お知らせします。最新情報を確認下さい。


古いお神札(ふだ)を返す場所はありますか?


お正月以外では、授与所窓口までお持ちください。当神社以外のお神札はお預かりしますが、袋やビニールまたは他宗教のものなどは、お断りしております。
詳しくは


お参りの正しい作法を教えてください。


まず鳥居で一度おじぎをします。その後、境内の手水舎(ちょうずや)で手と口を清めます。その後、ご神前にて二拝二拍手一拝の作法でお参りします。鈴とお賽銭のお納めは、お参りの前に行いますが、順番については特に気にする必要はございません。


歯固め石を拾ってもよいですか?


授与所にて、お清めを済ませた歯固め石をお分けしております。


引いたおみくじはどうするのがよいですか?


おみくじ掛けに結ぶのが一般的とされていますが、お持ち帰りになられてはいかがでしょうか。お手元に置き、神さまからのお言葉として時折読み返してみるのもよろしいかと思います。


捨てられない人形の処分をしてもらえませんか?


受付にてお預かりします。初穂料は45リットルのポリ袋容量を目安として、1袋につき3000円をお納めください。お正月期間は、ご遠慮いただいております。
詳しくは


御朱印帳はありますか?


当神社オリジナルの御朱印帳をご用意しております。


御朱印は何時まで受けられますか?


9時から16時30分まで受け付けております。祭典、行事等によりお受けできない場合は最新情報でお知らせします。


御朱印と御朱印帳の郵送はしてもらえますか?


郵送は行っておりません。お参りのうえお受けください。


いろいろな神社のお守りを持つのはよくないと聞きました。


神さま同士が喧嘩をすることはございません。さまざまなご神徳の神さまがいらっしゃいますので、複数のお札・お守りをお持ちになっても構いません。


お神札・お守りはいつ返したらよいですか?


●神棚におまつりするお神札や荒神さまの古いお神札は、新しいお神札をおまつりののち、年末年始に神社へお返しください。
●ご祈祷などでお受けになられたお神札・お守りは1年が経ちましたら、神社へお返しください。
●初宮詣や安産、合格などのお神札・お守りについては、期間をお気になさらず、その御祈願が成就するまでお持ちください。また、祈願の成就後も、特別な思い入れがある場合は、そのままお持ちいただいても大丈夫です。


お土産に持ち帰ったお守りは返さないといけませんか?


お受けになった神社へお返しするのが望ましいですが、遠方で難しい場合には郵送でお返しするとよいでしょう。旅行の記念に保管されたい場合は、粗末に扱うことのないようにしましょう。


お守りがほしいのですが、お参りに行けません。郵送してもらえますか?


原則として、お参りいただいたうえでお守りをお受けいただくようお願いしております。特別なご事情のある方はご相談ください。


神棚って何ですか?


家庭内における小さな神社と考えていただければよいでしょう。天照皇大神宮(てんしょうこうたいじんぐう)(伊勢神宮)、氏神神社、崇敬神社のお神札(ふだ)を、お社の形をした宮形(みやがた)に納め、おまつりする棚のことです。


神棚はどこに置けばよいですか?


神棚の前面が南から東を向く場所で、日常的にご家族が集まる明るい場所に設置しましょう。ご不明な点は、どうぞご相談ください。


お供え物は毎日とりかえるものですか?


本来はそうです。難しい場合には、1日と15日に新しいお供えをするよう、心がけるとよいでしょう。


お神札は毎年かえるものですか?


本来は、年末に新しいお神札をお受けになり、12月28日か30日にとりかえ、新年を迎えます。古いお札は、初詣の際に神社にお返しします。


喪中の間、神棚はどうしておけばよいですか?


忌中(亡くなられてから50日間)のみ、白い紙を貼っておまつりを控えます。


実家の神棚を処分したいのですが、どうすればよいですか?


神職がお家にお伺いし、これまでお家をお守りいただいたことへの感謝のおまつりを行います。お祓いを済ませた神棚は、その後神社にてご焼納します。お家でのおまつりが難しい場合には神社へお参りになり、お神札と神棚をお納めください。


氏神さまって何ですか?


古くは氏族(共通の祖先を持つ血縁集団)の守り神を氏神さまといいましたが、今日では住んでいる地域の守り神を指して氏神さまといいます。私たちの日々の生活をお守りくださる神さまです。


産土神(うぶすながみ)って何ですか?


今日では氏神さまと同じように考えられていますが、本来は生まれた土地をお守りくださる神さまを指して産土神さまといいます。


氏神さまにお参りするべきですか?


日々の生活をお守りいただいていることへの感謝の気持ちを込めて、ぜひお参りいただければと思います。


どこの神社が氏神さまなのか、わかりません


氏神さまの調べ方をご覧ください。


氏神さまに神主がいない場合、ご祈祷はどうしたらよいですか?


神職が常駐していない神社にはそこを管理する神社がありますので、まずはそうした管理神社をお探しになり(氏神さまの調べ方参照)、ご祈祷が可能かどうかご相談ください。ご願意によっては他の神社をお探しになってもよいでしょう。(例:合格祈願の場合 ⇒ 天満宮)


式後の会食はできますか?


会食を行うことは出来ません。


式には何名まで参列できますか?


30名までとさせていただいております。


外国人でも式を挙げられますか?


挙げられます。


神社で着付けできますか?


可能です。参集殿の一室を着付け室としてご利用いただけます。


衣装やヘアメイクなどをお願いできる業者さんはいますか?


ご紹介が可能です。
ローズベールブライダル


待合室はありますか?


ございます。親族紹介の場としてもご利用ください。


誓いの言葉をローマ字で対応していただけますか?


可能です。


申し込みの手順はどうすればよいですか?


まずはご連絡ください。新郎新婦と神社職員で打ち合わせを行います。
申し込みフォームへ


参列という形ではなく外から晴れ姿を見たい、お祝いしたいという友達がいるのですが、可能ですか?


可能です。


相結(あいむすび)で式を挙げたいのですが、参列定員を超えてはいけませんか?


新郎新婦を含めて6名までの参列となります。


相結で式を挙げるときの服装は?


平服でおいでください。


地鎮祭は氏神神社に依頼するべきですか?


地鎮祭はその土地をお守りくださる神さまへのおまつりですので、氏神さまにご依頼しますが、さまざまな事情により氏神さまにお願いできない場合はご相談ください。


建売住宅を買いました。地鎮祭をしていないので心配です。


「入居清祓」をご依頼ください。お家のなかに祭壇を設け、神さまをお招きしておまつりを行います。また各お部屋をお祓いし、ご家族の安全をご祈念します。


家の敷地から井戸が出てきました。必要ないので埋めたいのですが、お祓いが必要ですか?


「井戸清祓」を行います。井戸の前に祭壇を設け、井戸および水の神さまに、これまでお水を湛えてくださったことを感謝します。


庭の木を切ることになりました。お祓いが必要ですか?


樹木にも御霊が宿っていますので、「樹木清祓」を行います。特に大切にされてきた樹木には、おまつりを行って感謝を捧げます。


家の工事をしています。敷地内にあるお稲荷さんを移動させたいのですが。


施工の前後に遷座祭(せんざさい)を行います。移動先となる場所を清め、そこへお遷(うつ)りいただくことを神さまにご奉告します。お遷りいただいたのちに再び、無事に遷座を終えたことをご奉告します。


地鎮祭にはどんな服装がよいですか?


おまつりにふさわしい、きちんとした服装がよいでしょう。足元が悪い場合もございますので、お履き物にご留意ください。


地鎮祭の御礼はいつ渡せばよいですか?


おまつりが始まる前に玉串料(初穂料)として神職へお渡しください。祭壇にお供えします。


施主のみの参列でも大丈夫ですか?


地鎮祭には工事の安全祈願の意味がありますので、施工業者も参列されるのが望ましい形です。ご事情によりそれが叶わない場合には施主のみでも構いません。


地鎮祭を行う際、施主と施工業者は何を準備したらよいですか?


施主 玉串料 施工業者
必要に応じ、テント・椅子・奉献酒 等
※当神社では準備のご負担を考慮して、地鎮祭に必要な祭具類を持参しております。


地鎮祭のときにいただいたお神札(ふだ)はどうすればよいですか?


工事の安全祈願が込められておりますので、工事期間中はお住まいのお家にておまつりください。また、建物そのものの安全祈願も込められておりますので、棟木や屋根裏に取り付けるとよいでしょう。


新居のお祓いをしたいのですが。


「入居清祓」をご依頼ください。お家のなかに祭壇を設け、神さまをお招きして家内安全祈願のご祈祷を行います。同時にお家の各所を祓い清めます。


幽霊が出ました。お祓いしてもらえますか?


お家のなかに祭壇を設け、神さまをお招きして、災いが起きないようご祈祷を行うことは可能です。


神葬祭は神社で行うのですか?


神社では行いません。古くは故人のお家で行うのが一般的でしたが、現在は斎場や町内会館などで行います。


戒名のようなものはありますか?


「諡(おくりな)」をお付けします。出自や身分に関係なく、男性の場合には「比古(ひこ)」「大人(うし)」「翁(おきな)」、女性の場合は「比賣(ひめ)」「刀自(とじ)」「媼(おうな)」などになります。


無宗教だった故人を神葬祭で送りたいと思います。どうすればよいですか?


特別な手続きは必要ありません。ご相談ください。


五十日祭や一年祭を神社で行うことはできますか?会食は可能ですか?


参集殿年祭室にて行うことができます。また、式後の会食は出来ません。
神社境内地につき、ご遺骨のご持参と喪服でのご来社はご遠慮いただいております。
ご紹介は出来ます。


一年祭は命日に行うものですか?どこで行えばよいですか?


一年祭をはじめとして、三年・五年・十年・二十年・三十年・四十年・五十年の節目に行う年祭(ねんさい)は、命日に行うのが望ましいとされています。お集まりになる方のご都合により変更される場合は、命日より前に行うのがよいでしょう。お家でおまつりするのが望ましい形ですが、お墓(奥津城・おくつき)や霊園のホール、会食場などでも行うことができます。


葬儀をしませんでした。家では何にお参りしたらよいですか?


霊璽(れいじ)と呼ばれる御霊代(みたましろ)に故人の御霊をお遷しする遷霊祭(せんれいさい)を行う必要があります。詳しくはご相談ください。


先祖代々の霊璽がたくさんあります。ひとつにまとめることはできますか?


先祖の御霊(みたま)を「○○家先祖之霊」としてひとつにまとめることができます。その際には遷霊祭を行う必要があります。



喪中はいつまでですか?


故人が亡くなられた翌日から50日までを「忌中(きちゅう)」、1年間を「喪中」といいます。50日を過ぎると忌明けとなり、神社や神棚へのお参りを再開します。


喪中(忌中)の間、神棚と御霊舎(みたまや)へのおまつりはどうすればよいですか?


帰幽の奉告後、神棚には白い紙を貼り、御霊舎の扉を閉じて50日間(忌中)お参りを控えます。


喪中ですが、鳥居をくぐらなければ神社へお参りしてもよいですか?


喪中は一年間ですが、忌中の50日を過ぎましたら、お参りできます。


年祭には何を準備すればよいですか?


基本は①~⑤です。年祭を行う場所によって、準備するものが変わる場合があります。
基本:①霊璽 ②遺影 ③神饌(お米、お酒、お塩、お水、乾物、野菜・果物3種以上)④飾り用榊(一対) ⑤参列者名簿
※神饌は神社でもご用意できますのでご相談ください。
※玉串・大麻は神社よりお持ちします
自宅:①神饌と玉串を置くための机(目安として75センチ×50センチ程度の座卓)
会食場:①霊璽 遺影 神饌 玉串を置く机(目安として会議机1台) ②机にかける白い布
墓前:特にありません
霊園ホール:霊園にご相談ください


奥津城(お墓)には何と彫ればよいでしょうか?


一般的には霊号を付した故人のお名前(例:○○○○大人之命)、帰幽年月日、享年を彫ります。


五十日祭までに何を準備したらよいですか


霊璽は50日(忌中)の期間には仮の場所でおまつりし、忌明け後は御霊舎に納めておまつりすることとなりますので、神具店にご相談のうえ御霊舎や御櫝(おとく)をご用意ください。また埋葬の準備もお進めください。
神具店のご紹介 「水蓮堂」横浜市西区浜松町2-30(藤棚バス停際)
電話045(243)8150


